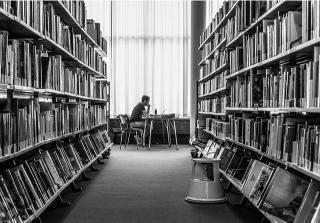この記事では、行政書士試験に一発で合格するための具体的な方法についてお話しします。難易度の理解から、予備校、通信教育、独学それぞれのメリット・デメリット、効果的な学習方法、そして合格に必要な心構えまで、多岐にわたる情報が網羅されています。この記事を読むことで、行政書士試験合格に向けた具体的な戦略と、学習を進める上で役立つ実践的なアドバイスを得られるでしょう。
行政書士試験の難易度と学習時間
行政書士試験はそこそこ難しいです。宅建と同じ感覚で入ってくると、後悔することになるくらい難しいので、そこは気を付けてください。
最低でもやはり800時間、900時間、だいたい1,000時間程度の学習時間を確保していくということが必要になってきます。そこをまず勘違いすると、なかなか合格できないと思います。
また2年越しでもいいという気持ちを持っている人もなかなか合格しにくいです。同じ1,000時間を勉強するにしても、2年で1,000時間を勉強すると非常に薄くなってしまいます。
結局、直前期のやり込み方というのが決まっているので、直前期にどんだけ時間を確保できるかというのが、行政書士試験に効率よく合格することにかかってきます。受けるのであれば、2024年に必ず決めてしまうという覚悟が必要です。長年かけて受かればいいという考えは捨てた方がいいと思います。
合格率は10%程度となっていますが、この中には司法試験組や司法書士を受けた方も含まれてきますので、元々の法律の素養の高い方も行政書士試験には参入してきます。
となると、もっと本当は合格率が低いんじゃないかと思われますが、逆に言ってしまえば、試験当日に十分な準備をしていない、また勉強法を間違えてそのまま試験会場に来ている人も半分くらいいるんじゃないかなと思います。
ですから、しっかりとやり込めば、合格率はそこまでめちゃくちゃ低いわけではなく、ちゃんとやれば半分程度は受かるんじゃないかと考えています。
予備校・通信教育・独学のメリット・デメリット
予備校、通信教育、独学、それぞれにメリット・デメリットがあります。
予備校の利点は、やはり教材を自分で選ばなくて良くて、向こうが用意したものをやり込めば合格しますよという点です。また、講義がちゃんとついてますから、それを聞けばある程度の内容は把握できます。これが最大のメリットだと思います。
その反面、勉強した気になってしまうというデメリットががあるんじゃないかと思っています。
実際、予備校を使って合格した人と独学でやった人の合格の点数には差がないんじゃないかなと。なので実際には、やり込めることというのはもう決まっていて、独学でもそれをやり込めば、予備校生には全然負けないくらいの合格点を取ることができます。全然恐れなくてもいいです。
予備校のデメリット
予備校のデメリットの1つとして捉えているのは、やはり授業というのは一方通行だという点です。
先生がこちらに向かって話しているのを1時間聞いていて、それが自分の力になるかというと、効率は良くないですよね。やはり過去問というのをスタートにして、自分が真剣にその問題に向き合って、その解決方法として六法を調べたり、テキストを読み込んで、「こういうことだからこうなんだね」という風にその繰り返しをしないと、やはり勉強というのは伸びていきません。
そうやって考えた時に、過去問をやりまくるというところを考えたら、別にその授業の講義に大量の時間を割かれてしまう予備校が果たして効率的なのかというと、僕はそこに関してはデメリットだと思っています。
独学のデメリット
独学のデメリットというのも当然あり、それはまず行政書士試験で最初の大枠の全体像を掴むのが非常に難しいという点です。
全体像が掴めてしまえれば、あとは過去問をやり込めるだけで合格するということになってきます。その過去問のやり込める手前の全体像を掴むのが非常に難しいです。
市販のテキストを買ってくると思いますが、それを頭から読んでいってもちんぷんかんぷんでさっぱり分からないです。
法律は、1個の単元を例えば留置権とかそこの部分を勉強しても、全体的な法律像が分かってないと理解がかなり薄くなってしまいます。
ある程度全体像をふわっと掴んだ後に、それを何回も何回も繰り返すことによって、だんだんそこの留置権の部分を後からさらに2回、3回、4回勉強することによって、ようやく固まって理解できるという状態になってきます。
最初の段階では、細かい人とか真面目な人とかは逆に不利になったりして、ある程度大雑把に適当にざっくり進んでいくということが必要になってきます。
独学のメリット
独学のメリットというのは、なんと言っても無駄な授業がないとか、通学の時間がないとか、お金がかからないというところだと思います。
無駄な授業は結構もったいないです。独学は自分のペースでやりますから、「ここ分かってる」という授業をダラダラ聞いていても、それは時間に対する効率は非常に良くありません。900時間から1,000時間の学習時間というのは、主にそれを過去問の1個1個の足の理解に費やしていかないといけないのです。
講義を聞いて全体の理解をするという時間は、極力減らした方がいい思います。または、そういう講義で聞いたりする学習というのは、自分の移動時間とか、耳で学習する、つまり机についてする時間以外に設けた方がいいんじゃないかと思っていて、極力過去問を解きまくる方が伸びやすいです。
独学のデメリット
独学のデメリットはないです。
逆に予備校を使っちゃうと、予備校の講義をいっぱい勉強したら勉強した気になっちゃって、実は過去問のやり込みが独学生より少なくて、それで点数が独学生に負けるということも十分あります。なので、独学でも全然いいです。
効果的な学習方法と参考書
最小限の教材をやり込め方がいいと考えています。必要最小限のものは、まず合格の基本書です。これはいろんなところが出していますが、僕の場合は合格革命を使ったので、合格革命の基本書です。
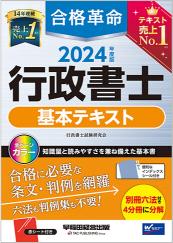
引用元:https://bookstore.tac-school.co.jp/e-book/detail/055104
問題集ですが、合格革命の基本問題集は非常に問題が薄くて、それだけでは不十分です。なので、合格革命の基本書と肢別過去問集、これが一番大事です。この1冊に行政書士の合格に必要な知識が全部詰まっています。この1つ1つの足を全部理解して、暗記ではなくちゃんと理解すれば合格するようになっています。
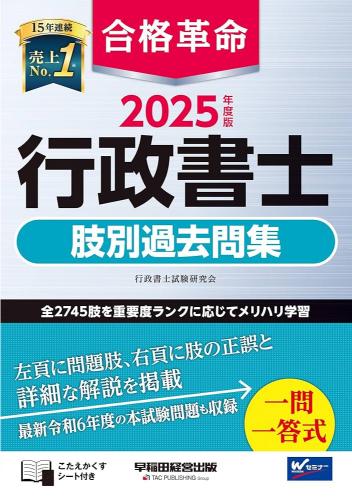
引用元:https://www.amazon.co.jp/合格革命-肢別過去問集-2025年度版-全2745肢を重要度ランクに応じてメリハリ学習-早稲田経営出版/dp/4847152115
次に必要なのが、10年分の過去問集です。
これはレックから販売されていて、最新版が出たらそれも買った方がいいです。なぜ過去問が2つ必要なのかというと、肢別過去問集は1個1個の足の知識を習得するもの、そして10年分の過去問集は行政書士試験がどういう試験なのかを理解するのに必要なのです。
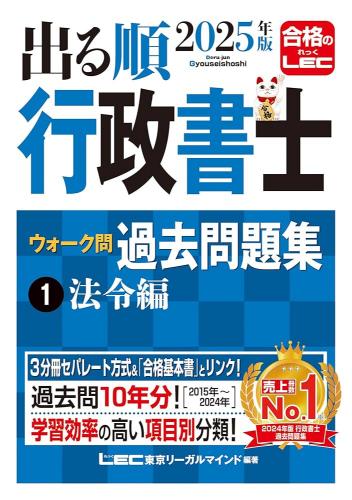
引用元:https://www.amazon.co.jp/2025年版-出る順行政書士-ウォーク問-法令編【3分冊セパレート・過去10年分】-出る順行政書士シリーズ/dp/4844958747
行政書士試験は絶対評価試験と言いながらも、10%程度しか合格者を出さないようになっていますから、過去問から全部出しちゃうとみんな合格してしまいます。
過去問ベースには作っているけれど、過去問の知識が完璧に理解できている人じゃないと解けないように、難しい問題が中に散りばめられたりします。
それがちょっとではなく、結構多くの数が「こんなとこ誰も知らないよね」というのを問われたりするんです。だけど、しっかりとこちらの知識を習得して理解している人であれば、正解にたどり着けるかなというような問題構成になっています。ギリギリたどり着けるような最後の2択で迷って、法的思考力を見抜けた人じゃないと正解できないような感じです。
とはいえ、6割正解すれば合格ですから、全ての問題を解く必要はありません。
捨て問というのも多く含まれてきて、合格する受験生でも解けない問題がたくさん出題されます。なので、その捨て問を見切れるためにも、この肢別過去問の問題を全部理解しておけば、「僕が知らない知識が問われている」ということに気づくんです。ということは、今まで自分が勉強した学習の中では、この中だとどれが妥当か、妥当ではないかの判断がつくということになります。
効果的な学習方法
学習の要となるのは、合格革命の肢別過去問集を回すことです。
1回や2回回しただけでは人間は絶対に頭に入りませんし、先ほども言ったように、一部分だけを理解しても全体が見えないと理解できません。なので、何回も何回も回さないと、ここの理解が深まらないんです。5周、6周としているうちに、自分が理解したつもりだったところの新たな気づきなどが必ず出てくるので、5、6周が必要になってきます。
暗記学習のポイントと注意点
条文の丸暗記というのもある程度必要になってきますが、それを最初の段階から使用すると非常にきついです。
実際に六法の条文なんて人間の頭ではすぐには暗記できません。
どうするかというと、暗記ではなく染みつかせるんです。何回も何回も足別過去問を回転させるということは、何回も同じ問題を見て、同じ条文を引きます。「またこの条文だ」ってことで何回も見ていたらそれが染みついてくるんです。暗記じゃなくて染みつくという感覚が大事です。
暗記学習の時期はいつ?
覚えるのは本当に辛いですし、最初の段階では特にやらなくていいです。
覚えるのは実際いつやるかというと、何回も何回も回転して染みついた状態の直前期、10月とか11月になって、「これずっと何回も見て、最後は覚えなきゃしょうがないな」という最後の直前で一気に丸暗記の詰め込みをやるんです。そこまでは見るだけで終わりです。それを暗記しようとするのは辛いですし、しなくていいと考えます。
学習効率と学習範囲・学習時間についての注意点
この肢別問題集を完璧に理解するのに半年まるまるかかりました。
知識が足りないなどと思う人もいますが、それだけの知識だったら1,000時間では絶対足りないことになります。
司法書士の勉強もしないと行政書士の問題には立ち向かえないとか、司法試験並みの問題集を持ってきて、それで民法を勉強しないと解けないという人もいますが、そんなことはありません。そういうことを聞いているのが行政書士試験ではありませんからね。その勉強をして合格しようとすると、多分1,000時間じゃなくて3,000時間とか4,000時間とか必要になってきて、効率が悪いです。
なので、効率よくスパッと受かってしまうためにも、肢別過去問集を回して1,000時間で合格しましょうという話になってきます。
それ以外に必要な教材は特にありません。Googleで分からない論点を調べたり、YouTubeで検索したりすると出てきますので、その都度、その単元の分からないところを動画で調べてみるということをすると、別に予備校の教材がなくても、予備校の講義動画がなくても、独学で全然足りるんじゃないかと僕は思っています。
予想問題集について
予想問題集というのがありますが、これも夏くらいになったらやるものです。
「過去問からはもう出題されない」と思って予想問題をやった方が効率がいいという考え方がありますが、それは大間違いで、予想問題はあくまでも予想です。
それがズバッと当たらなくて、ふわりとなんか似てる論点が出たから当たったというような、全く同じ聞き方をされないと結局解けなかったりするので、予想問題をするよりも過去問の知識を理解した方がはるかに効率がいいです。
予想問題集よりも過去問を完璧に仕上げよう!
これも多くの予備校の先生なども言うと思いますが、予想問題集を一生懸命回すよりも、やはり過去問をまず完璧に仕上げましょう。
多くの受験生は過去問も大体仕上がっていないくせに次の教材などに行くんです。そもそも本当に完璧に理解できていますか?これを全部完璧に理解にしていたら、僕の取っている点数、記述抜きで180点とか、トータルで200点オーバーは全然できるんです。なので、それ以上の教材は必要なく、効率が悪いのでやめた方がいいと思います。
六法について
六法は必要だと思います。中には使わなかったという人もいますが、僕は使った方がいいと思います。
ケータイ行政書士六法という薄っぺらいのがあり、これは非常に良かったです。
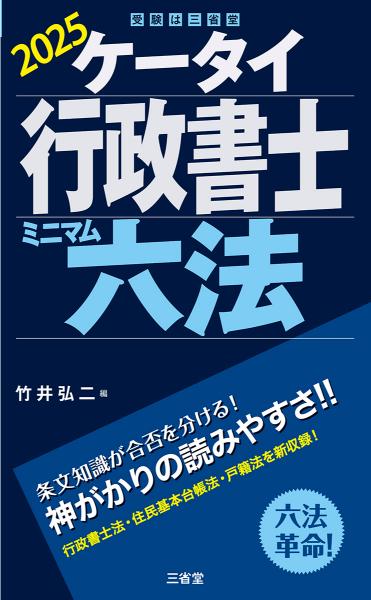
引用元:https://www.sanseido-publ.co.jp/np/detail/32559/
ケータイ行政書士六法の使い方と注意点
ただ、これ歯抜けの条文がいっぱいあるので、結構イライラします。
「なんでこんな大した条文が載ってないんだ」となりますが、それは自分で書き足すようにして、どんどんこの六法を仕上げていってください。
自分でページを増補して紙をくっつけて、覚えなければいけない判例とか、「またこの大事な判例が出たね」という時にはそれを書いて、その判例を直前期に覚える準備をしておくことです。
六法はケータイ六法がいいと思います。他にもデイリー六法などもありますが、これはやはり分厚いし持ち運びも大変です。中には分冊している人もいますが、字が小さいし、こちらの六法はかっこ書きがないので非常に読みやすいんです。
あとメリハリで大事な部分に関してちょっと色を変えて書いてくれたりしているので、本当に受験生向けには作られています。歯抜けなのはむかつきますが、その分使いやすいというメリットがあるのでいいと思います。
基本書にも六法はついていますが、かっこ書きの面とか色分けの部分がなかったりという部分は違うので、やはり僕はこっちの方が使いやすいかもしれないと思っています。
記述問題対策について
記述の対策はみんな心配されますが、とりあえずそんなに心配しなくていいです。
まずは肢別の理解をしてください。これを完璧に理解した状態で、夏くらいになったら、その論点を本当に理解しているかというような投げかけの形で大丈夫です。
合格に必要な考え方
合格に必要な物事の考え方というものがあります。
行政書士試験を知識の山で対応しようとしている人や、根性の面でも生半可な人は受からないです。
先ほども言ったように、「2年越しでもいいな」ということを夏などに思ってしまう人がいますが、これも駄目です。必ず1年で受かった方が本当に効率が良いです。
「どうせ今年だけじゃなくて来年も受からないだろう」と思ってしまいます。なので、2年とか3年とかそういう長期戦ではなく、必ず今年決めてしまうという覚悟が必要です。そのためには、自分の人生をかけて、自分の全てをかけて頑張るくらいの気持ちがないと、やはり合格することは難しいんじゃないかなと思います。
行政書士試験を勉強しているから自分のためになっていると思っているかもしれませんが、これはあくまで机上の空論で、実はそんなに自分のためになりません。
行政書士に合格したところで、実際に役場に行って申請などをする時にも、本当に何も知らない超ウルトラスーパー素人みたいな状態ですから、早く実務をやって自分をもっと成長させるためにも、こういう資格試験みたいなものはスパッと一発で終わらせてしまうという考え方がどうしても必要になってきます。
まとめ
- 行政書士試験は800〜1,000時間の学習時間が必要
- 独学でも十分合格可能、過去問を徹底的にやり込むことが重要
- 最小限の教材(基本書、肢別別過去問集、10年分過去問集、ケータイ六法)を徹底的に繰り返す
- 直前期に条文の丸暗記や記述対策に集中する
- 「今年で必ず合格する」という強い覚悟が必須
行政書士試験の合格は、正しい方法と強い覚悟があれば手の届く目標だと私は考えています。今回お話しした学習方法と心構えを実践し、効率よく合格を掴み取ってください。このチャンネルでは、行政書士試験合格に向けて必要な情報を時期に応じて配信していくので、ぜひチャンネル登録とTwitterのフォローをお願いします。